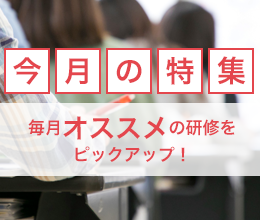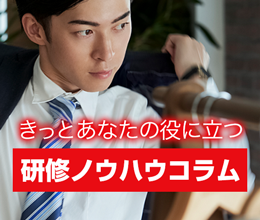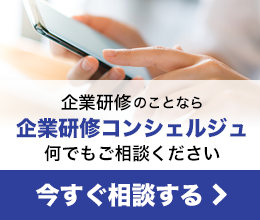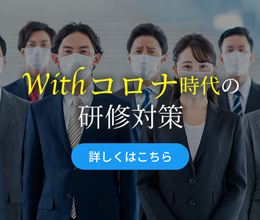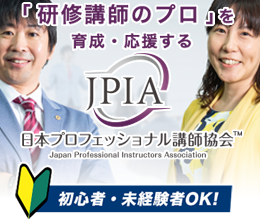【一般社員向け】ハラスメントゼロの組織づくり研修自分と相手の認識のズレを防ぐと職場はもっと働きやすくなる/3時間

こんな課題に対する研修です
本研修は「うちの会社でもあるある…」と誰もが共感する職場の課題を出発点にしています。
ハラスメントは一部の悪意ある行為だけでなく、世代や価値観の違い、何気ない言葉の選び方からも生まれます。多くのトラブルは「誤解」や「モヤモヤ」を放置した結果、深刻化していくのです。だからこそ必要なのは、知識だけでなく“相手の受け取り方を想像する力”を育てること。
本研修では、一方的に「やってはいけない」を押しつけるのではなく、「なぜ伝わらないのか」「どこですれ違うのか」を体感しながら、互いの違いを理解する視点を養います。その結果、指導に自信を持てる管理職が増え、若手社員も安心して相談や発言ができるようになります。小さな行動変化が連鎖し、安心して働ける職場づくりや離職防止、組織全体の信頼関係強化へとつながります。
対象者
一般社員
研修の期待される効果

・価値観や世代の違いから生じる発言の受け取り方のズレが誤解がある。
・不満があっても「どうせ言っても変わらない」と思い込み、モヤモヤを抱えたままの社員が多い。(離職の要因になっている可能性がある)
・会社の取り組みが管理者中心にとどまり、現場の社員には本気度が伝わりにくい。
・行動変化が一部に限られ、組織全体に広がらず、安心できる職場づくりにつながっていない。

・価値観の違いから生まれる誤解やトラブルの芽を早期に減らす。
・相談や対話のきっかけを自然に生み出し、モヤモヤを抱え込まない風土をつくる。
・会社の本気度を社員に示し、組織への信頼を高めるメッセージになる。
・小さな行動変化を全体に広げ、安心して働ける職場づくりへと結びつける。
研修プログラム例
ハラスメントではないかとモヤモヤしたことの共有。
同じ言葉でも受け取り方が人によって違うことを理解し、研修への関心を高める。
【内容】
・研修の目的共有
●ワーク①:ハラスメントモヤモヤシェア
2.ハラスメントの正しい理解
ハラスメントの定義、法令の基礎知識紹介。
知識不足から生じる誤解を防ぎ、正しい理解を持つことが行動改善の第一歩になる。
【内容】
・パワハラの定義
・6類型の解説
・ハラスメントが起きやすい環境を理解する
・ハラスメントの要因・根本原因
3.ハラスメントの誤解を解く(グレーゾーンの正しい理解)
「指導」と「ハラスメント」の線引きが曖昧なため、グレーゾーンを体験的に学ぶことで判断力を養う。
言った側と受けた側の認識ギャップに敏感になる力を養い、誤解や不満を減らし、不要なトラブルの芽を早期に防ぐ。
【内容】
・正しい指導とパワハラの線引き
・過剰性・頻度・場所の観点
●ワーク②:ケース判断
4.自己理解:他者理解「思考の癖」を理解する
人は性格や思考のクセ、文化・背景によって同じ出来事でも受け止め方が大きく異なることを学ぶ。
人は誰でも「思考の癖」があることを理解し、「自分の基準=他人の基準ではない」ことを知る。
感度の違いが誤解や感情のすれ違いを生むことを体感する。自分が「言われて嫌なこと」でも「嫌でない」と感じる人がいたり、その逆があることを知る。過去の嫌だった言動は、相手の悪気ない言動だったかもしれないことを理解する。
【内容】
「私のことを分かってもらえない」
「上司の価値観が理解できない」をなくす
・外向型・内向型
・感覚型・直感型
・思考型・感情型
・判断型・知覚型
●ワーク③:言われて嫌なこと・されて嫌なこと
5.アンコンシャスバイアスの払拭
自分の無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)が、自分の意図に反して相手を傷つける可能性があることに気づく。
アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)がどのように発生するのかを知ることで、出来事の捉え方を変え、アンコンシャスバイアスの払しょくにつなげる。
<管理者向けのアンコンシャスバイアスとの違い>
管理者:バイアスを抑え、公平なマネジメントを行う
一般:個人として気づきを持ち、人を気付付けないように配慮する。誤解や自分のモヤモヤを減らす。
【内容】
「脳のバイアス」が「分かり合えない」を作る
●ワーク④:「無意識に思い込んでいること」診断
・SPARK理論(感情のトリガー理解)
・出来事の捉え方を変える
6.学びを職場に活かす
「今日学んだことを職場でどう使うか?」を一人ひとり考え、ワークシートに記入。
グループ共有・グループ発表 バディシステム:研修終了1か月後にバディと一か月の取り組みを報告し合う。
【内容】
「明日から取り組む宣言」ワーク(=職場への具体的な変化・アクションに直結)
●ワーク⑤:「明日から取り組む宣言」ワーク
7.まとめ
講師よりまとめメッセージ
「安心して働ける職場づくりは、若手も担い手である」「あなたの小さな一歩が、離職防止や風通し改善につながる」
【内容】
講師よりまとめ
▼研修のウリ!
自分にも相手にも思考のクセがあることを実感し、世代やバックグラウンドの違いにより「されて嫌なこと」が人それぞれ異なることに気づけます。単なる知識習得ではなく、具体的なワークを通じて相手に歩み寄る姿勢を実践的に学習できます。「思い込む」「決めつける」行動から脱却し、多様な価値観を受け入れる柔軟性を養います。結果として職場での誤解が激減し、お互いを理解し合える信頼関係の構築が可能になります。
お客様の声
知識を学ぶだけでなく、体感ワークを通じて“自分ごと化”できる点が非常に効果的でした。受講後すぐに若手から「自分も悪気なく人を傷つける言動をしていたかも?と思うと上司の発言に寛容になれた」という声が上がり、職場全体の雰囲気が少しずつ前向きに変わり始めています。
講師からのメッセージ

AOI SHUTTO宗東 青依
管理者だけに研修をしてもハラスメントはなくなりません。一般社員も自分や相手の「思考のクセ(アンコンシャスバイアス)」を理解し、価値観や感じ方の違いを認識することが必要です。
上司への誤解や不信感を「悪意ではなく良かれと思っての行動」と捉え直せることでこそ、信頼関係は強まります。
管理者は境界線を学び、一般社員は相互理解を深める。つまり、ハラスメントの改善は「両輪」で取り組むことで、
①即効性:現場で相互補強され定着する
②リスク低減:誤解を早期に抑えられる
③風土づくり:共通言語で安全な職場を築く効果が得られます。
この研修について問い合わせる