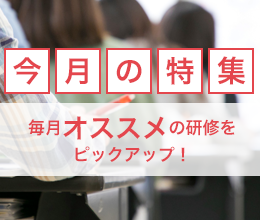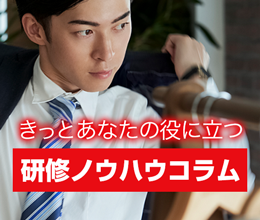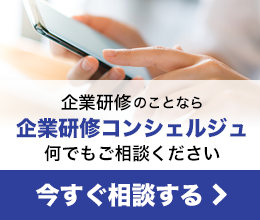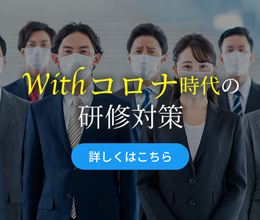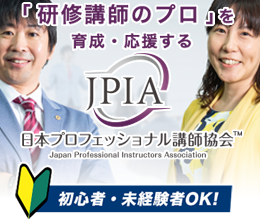ハラスメントを防ぐアサーティブ・コミュニケーション信頼と安心の職場をつくる伝え方/2時間程度

こんな課題に対する研修です
本研修「アサーティブ・コミュニケーション研修」は、現在の日本企業が抱えるハラスメントおよびコミュニケーションの課題に対し、実践的かつ本質的なアプローチで解決を図るプログラムです。
「指導」と「パワハラ」の境界が曖昧な現場においては、主語の使い方や非言語表現の工夫を通じて、相手に伝わるフィードバックの仕方を習得できます。また、感情の扱いに不慣れな職場風土に対しては、怒りの背景にある「大切にしたいこと」への気づきを促し、自他を尊重した表現力を高めます。
多様化する価値観に対応するため、攻撃型でも自己抑制型でもない、相互理解を重視した“アサーティブな態度”を実践的に学びます。知識習得にとどまらず、具体的な言動レベルでの行動変容を促す内容により、心理的安全性の高い職場づくりに貢献できる研修です。
対象者
若手~管理職、経営者
研修の期待される効果

1.指導や注意が「パワハラ」と受け取られることへの不安がある
2.部下・後輩へのフィードバックが苦手、伝わらない
3.感情に流されてしまう場面での不適切な対応がある
4.コミュニケーションのすれ違いによる人間関係の悪化や生産性低下の懸念がある
5.我慢や遠慮により、本音が言えない職場風土である

1.上司やリーダーが部下を叱る、評価する際、攻撃的に受け取られずに伝えたいことを伝えられるようになる
2.主語や非言語表現を意識し、「伝わる」コミュニケーションが実践できるようになる
3.怒りの背後にある「大切にしたい価値観・願い」に気づき、感情をコントロールした建設的な対応ができるようになる
4.自他の気持ちを尊重した表現を行うことで、誤解や摩擦を防ぎ、職場の人間関係が円滑になり、生産性向上が期待できる
5.「ノンアサーティブ(自己抑制型)」な態度から脱し、率直かつ配慮のある自己表現ができるようになる
研修プログラム例
パワハラ・セクハラ・マタハラの正しい定義や具体的な事例を学び、自身の言動がハラスメントに該当するかを客観的に判断する力を身につけます。曖昧になりがちな基準を明確に理解し、職場での予防と適切な対応に活かせます。
【内容】
・パワーハラスメントの定義と3要件の解説
・パワハラの6類型と具体例の紹介
・職場で実際に起こりうる事例をもとにした判定ワーク
・セクシャルハラスメントの定義と判断基準
・マタニティハラスメント(マタハラ)の理解と注意点
・ハラスメントが従業員と企業に与える影響の解説
・ハラスメントを起こさない職場づくりのポイント
2.ハラスメントを防ぐためのアサーティブ・コミュニケーション
自分も相手も尊重する「アサーティブ・コミュニケーション」の実践を通じて、攻撃的・回避的な表現から脱し、信頼関係を築ける対応力を養います。怒りなどの感情の背景にある価値観を理解し、適切に気持ちを伝えるスキルを学ぶことで、職場での誤解や摩擦を防ぎ、健全な人間関係と安心して働ける環境づくりに貢献します。
【内容】
・自己表現スタイルの3類型の理解(アグレッシブ・ノンアサーティブ・アサーティブ)
・自分のコミュニケーション傾向を振り返るワーク
・怒りの感情のメカニズムと背景にある価値観の理解( 感情を抑えるのではなく、自覚と対処を学ぶ)
・アサーティブな表現方法の3ステップ
・「主語の使い方」や「非言語表現」による印象の違いの体感
・部下や同僚への注意・指導の実践ワーク
▼研修のウリ!
本研修は、ハラスメントを未然に防ぐ「アサーティブ・コミュニケーション」を実践的に学べるプログラムです。
信頼関係を築く伝え方に加え、怒りや不満などネガティブな感情の背景にある価値観に気づき、適切に対処する力を養います。体験ワークを通じて、明日から使える実践力が身につきます。
お客様の声
・仕事、私生活問わず活かせる内容でした。
講師からのメッセージ

YOSHIKO USUI臼井 淑子
この研修では、自分も相手も大切にする「アサーティブ・コミュニケーション」を学び、ハラスメントの芽を摘み、信頼関係を築く力を身につけていただきます。怒りや不満などの感情の背景にある「本当に大切にしたいもの」に気づくことで、より本質的な対話が可能になります。
私自身、企業の相談窓口や人材育成の現場で多くの方の声に触れてきました。だからこそ、一方的な知識ではなく、実感を持って役立つ内容をお届けしたいと思っています。
この研修について問い合わせる