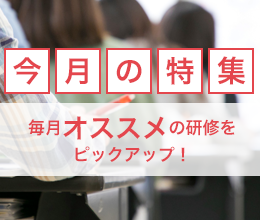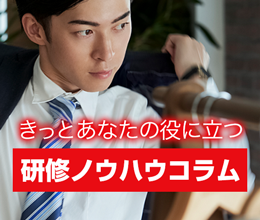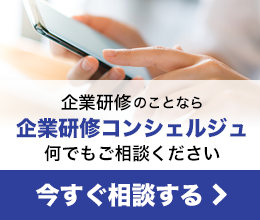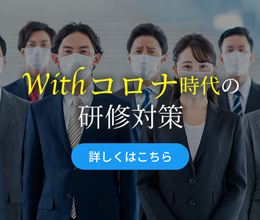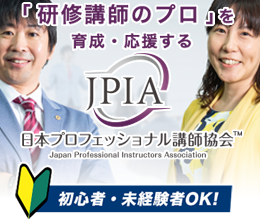ハラスメント「ハラスメント」とは?

「ハラスメント」とは
ハラスメントとは、「嫌がらせ」「いじめ」のことであり、
相手に不快な思いをさせる行為のことを言います。
ネットで「ハラスメント」と検索すると50種類以上出てきますが、
どういう言動で相手に不快な思いをさせたかによって
○○ハラスメントとなります。
職場での代表的なハラスメントは、「セクシュアルハラスメント」
「マタニティハラスメント」「パワーハラスメント」の3つです。
自分ではそんなつもりはなかったと、無自覚のうちに
ハラスメント行為をしていることもありますので、
どういう言動がハラスメントになるのか、正しく理解することが
大切です。
知らなかったでは済まされないのがハラスメント問題です。

注目される背景
都道府県労働局の相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」
に関する相談件数は年々増加し、ハラスメントが原因で
発症した心の病も増え続けています。
ハラスメントが原因でメンタル不調になり、職場で能力を
十分に発揮できないだけでなく、休職や離職、自殺を誘引するなど
組織の人事上、見過ごすことができない事態になっています。
ハラスメントによる影響は、被害者だけではありません。
ハラスメントと認定された加害者は信頼を失くし、これまでの
キャリアを棒にふることになります。
周囲へのインパクトも大きく、ハラスメントがある職場の生産性は
低下し売上にも影響します。
企業にとっては、人材流出、採用難、取引先からの信用低下にも
つながります。
ハラスメントは個人間の問題ではなく、組織の問題です。
明るく働きやすい職場づくりのためにはハラスメント対策は
欠かせない要素の1つです。
参加者のこんな課題を解決します!
・どういう行為がハラスメントにあたるのか正しく理解したい・組織で取るべき対応策、ルールを見直したい
・ハラスメントを防止するには、どうすればいいのか知りたい
・ハラスメントにならない部下への注意・指導のポイントを学びたい
・ハラスメントを受けないためにどういう点に気を付ければいいのか知りたい

研修を通して学べること
ハラスメントというと上司から部下へ向けた言動というイメージを
お持ちの方が多いかと思いますが、上司からだけではありません。
同僚や部下がハラスメントの行為者になることもあります。
自分ももしかしたらしているかも? と当事者意識を持つこと。
個人が持つ思い込みや、決めつけがハラスメントの要因の1つです。
ハラスメント行為者とならないためにどういう点に
気を付ければいいのか、ご自身がハラスメントを受けないために
日ごろから何をどう気をつければいいのかを理解して
実践していただくことが大切です。
ハラスメント対策を通して、お互いを思いやることができる
組織づくりを行っていただきます。
ハラスメント研修では、管理職、一般職の方に向けて
どういう行為がハラスメントになるのか正しく理解する
ハラスメントにならない注意指導のポイントを学び部下育成に
つとめるハラスメントをしない、させないための職場で
必要なコミュニケーションについて学びます。
カテゴリから探すFind by CATEGORY
人気の研修Popular Training
-
ハラスメント管理職向け
ハラスメント研修
現代社会において、ハラスメントは職場において深刻な問題となっています。 2020年に大企業に対してパワーハラスメント対策が義務化された後も...
-
アサーティブコミュニケーションハラスメント
ハラスメントを防ぐアサーティブ・コミュニケーション
本研修「アサーティブ・コミュニケーション研修」は、現在の日本企業が抱えるハラスメントおよびコミュニケーションの課題に対し、実践的かつ本質的な...
-
ハラスメントマネジメント部下育成
ハラスメントゼロを目指す指導力とマネジメント研修
良好な人間関係は職場の働きがいを高め、人材不足の解消とお客様満足度に貢献します。 時代の変化と共にアップデートが求められる「ハラスメントに...
-
クレーム対応ハラスメント管理職向け
医療カスタマーハラスメント対応 研修
医療現場で弁護士や警察と連携する事例が増えています。患者からの要望やクレームが日々複雑化し、精神疾患を抱えた患者クレームが増えてきています。...
-
ハラスメント部下育成階層別研修
チーム医療~ハラスメントゼロを目指す指導力とマネジメント研修
医療現場では医師、看護師、コメディカル、事務とスタッフ間の連携が不可欠です。 良好な人間関係は医療現場の働きがいを高め、人材不足の解消と患...
-
ハラスメント
ハラスメント防止研修(セクハラ・育介ハラ・ジェンダーハラスメント編)
「健全な職場環境の構築を目指して」 本研修は、職場におけるハラスメント問題に対処し、全従業員が安心して働ける環境を構築するために実施します。...
-
ハラスメント管理職向け
ハラスメント防止研修(パワハラ編)
「安心して働ける職場を目指して」 現代の職場では、パワハラが従業員の精神的および身体的健康に深刻な影響を与えることが多く、組織全体の生産性や...
-
コーチングスポーツコミュニケーションハラスメント対人関係構築力
スポーツコミュニケーション
様々なスポーツの現場において指導者のコミュニケーションの質の向上が求められています。スポーツ指導者は自身の成功体験をもとに熱血指導を行うこと...
-
ハラスメント
管理職向けカスタマーハラスメント研修
・カスタマーハラスメントに対して判断基準がわからない ・カスタマーハラスメントに対して適切な対応方法がわからない ・カスタマーハラスメン...
-
コミュニケーション基礎ハラスメント
ハラスメント対策講座「アンコンシャス ・バイアス」
近年、露骨なハラスメントは減少傾向にありますが、無意識の偏見や思い込みに起因する「自覚なきハラスメント」が新たな課題として浮上しています。善...
-
クレーム対応ハラスメント
「クレーム初期対応・ハードクレーム対応」講座
近年、お客様からのご意見やクレーム内容はますます複雑化しています。2020年と2022年に厚生労働省がカスタマーハラスメント対策のガイドライ...
-
ハラスメント
パワーハラスメント撲滅研修
パワーハラスメント研修で最も要望が強い「何が一体パワハラなのか?」、そして「パワハラに対してどのように対応するか」に重点をおいた研修です。 ...