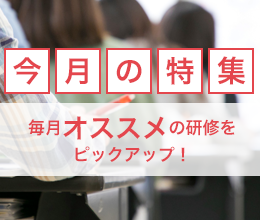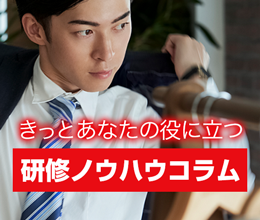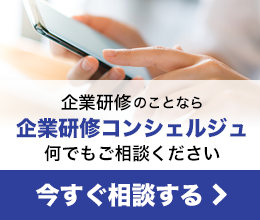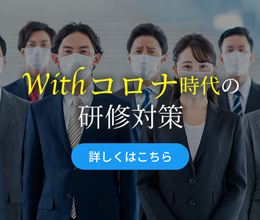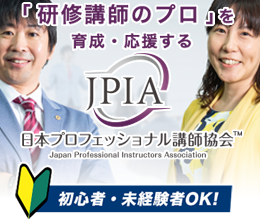こころのケアで輝く未来へ仕事と生活のバランスを整える心のメンテナンス術/6~8時間

こんな課題に対する研修です
1. ストレスや不安の悪化
従業員のストレスが高いまま放置すると、精神的な負担が蓄積し、メンタル不調が深刻化するリスクが高まります。
2. 生産性の低下
ストレスや不安が原因で集中力や業務効率が低下し、チーム全体の生産性が下がる可能性があります。
3. 離職率の上昇
精神的な健康が支えられていない環境では従業員の満足度が低下し、離職率が高まることが予想されます。
4. 職場環境の悪化
ストレスやコミュニケーション不足により、チームの雰囲気や協力関係が悪化しやすくなります。
5. コンプライアンスリスク
企業が従業員の健康を守るための義務を果たさない場合、法的な問題や社会的な批判を受ける可能性があります。
6. 業績への影響
精神的な健康不調が増える事で欠勤や長期休職が増加し、業務運営全体に影響を与える可能性があります。
対象者
若手~管理職、経営者
研修の期待される効果

1. 従業員のストレスレベル:ストレスの原因や対処法への理解不足のため、問題が深刻化するリスク。
2. 職場の雰囲気:精神的な不調をオープンにできず、チーム内のコミュニケーションが希薄で摩擦が生じやすい。
3. 自己ケアの習慣:自分の精神的健康を後回しにしがち。健康的なライフスタイルの維持が困難。
4. モチベーションと生産性:ストレスや精神的な負担から業務効率が低下。長期的には離職率の上昇リスク。

1. 従業員のストレスレベル:ストレスの兆候を早期に把握でき、効果的なストレス管理法を実践することで負担が軽減。
2. 職場の雰囲気:メンタルヘルスについてオープンな話し合いができる風土が形成。チーム内での相互支援が促進される。
3. 自己ケアの習慣:自己理解と自己ケアの能力が向上。生活習慣を改善し、持続可能な健康管理が定着。
4. モチベーションと生産性:業務への集中力と意欲が向上。健康的な職場環境が離職率の低下につながる。
研修プログラム例
・統計やデータを用いて個人の心の健康が組織に及ぼす影響について考える。
・メンタルヘルスについての「個人の問題である」とか「その人が解決すべき」という考え方を改めてもらい、組織全体が取り組むべきことであるという認識を持ってもらいます。
・「自分は大丈夫」ではなく、誰でもメンタル不調になる可能性がある事を自覚してもらいます。
【内容】
・自己紹介
・職場の5人に1人が何らかのストレスや心の問題を抱えいる現状を確認。
・何らかの対応をしないと生産性の低下や人材流失の原因となり、職場のパフォーマンス」や士気にも大きな影響を与えてしまう。
・職場で導入できる改善例を、ワークで考えてみる。
2.メンタルヘルスに関する基本知識
・ストレスのメカニズムやその影響
・脳(心)と身体の深い結びつき
・日常生活の改善によるメンタルヘルスの維持法
ストレスや不安を感じる場所=脳のメカニズムを知ることで、効果的な対策を講じることができるようになります。
メンタル不調になる前に身体の健康状態を把握し、問題点の抽出と改善策を講じることでうつ状態を未然に防ぐことができます。
【内容】
・意外と知らない脳の働き
・神経伝達物質とホルモンの違いと働き
・自律神経(交感神経・副交感神経)に支配されている身体と心を可視化する(レジリエンスチャートのワーク)
・生活改善(睡眠・栄養・呼吸・運動・趣味・会話など)で身体と心を安定させる
3.ストレス対処法の実践
・感覚を通して自分の状態に気づく。感情ではなく感覚に注目するセルフカウンセリングを学ぶ。
・急激なストレスにさらされると「闘争反応・逃走反応・凍り付き反応」にほとんどの方が当てはまります。しかし、ストレス耐性の高い方は「冷静沈着な平常心」を保つことができます。
・自分に合ったセルフカウンセリング技法を身に付けると、自分の心を守ると同時に雰囲気の良い快適な職場づくりに貢献してもらえます。
【内容】
・ポリヴェーガル理論から自分のタイプを知る
・セルフコンパッションの技法から五感を用いたリラクセーション実習をおこなう
・呼吸法やマインドフルネス瞑想・レーズンエクササイズの体験
4.コミュニケーションワークショップ
・自分自身の”考え方の癖=認知の歪み”を知り、多様な価値観を受け入られる「柔らか頭」を手に入れる。
・人は誰でも無意識の偏見や思い込みで偏った見方をしています(アンコンシャスバイアス)それにより、自分や周囲の人の可能性を狭めたり、誰かを傷つけています。
・自分の中の認知の歪みを知り、それを解消することで多様な価値観を受け入れて、相手を受容することが出来るようになると人間関係の改善が出来てきます。
【内容】
・自分の中のアンコンシャスバイアスチェックをおこなう
・認知行動療法の紹介とその活用法
1. コラム法:ストレスを感じた出来事や感情、自動思考を記録し、それに対する反論や新しい視点を考える
2. 認知再構成法:ネガティブな思考の偏りを修正し、柔軟な考え方を身に付ける
3. セルフモニタリング:自分の行動や感情を記録し、パターンを把握する
5.ケーススタディとグループディスカッション
・仮想のケーススタディを出しますが、職場の問題点やケースを出すことができれば、それに切り替えて実践的なコミュニケ―ワークを行うことも可能です。
・ストレスの本質は人間関係にあります。コミュニケーション改善が出来てくれば、必然的に職場環境が改善でき、心理的安全性の保たれた職場へと変わっていくことができます。
【内容】
・仮想のケーススタディを用いて、解決策をグループで考える
・シナリオを用いたロールプレイングでの実践的なトレーニング
・同僚や上司との健全コミュニケーション法(傾聴技術や共感的な対話)
6.研修振り返り
・参加者同士での意見交換
・研修内容の振り返りと「踏み出す一歩」=行動変容の宣言をおこなう
▼研修のウリ!
1. 実践的: 日常で使えるストレス管理スキルやリラクゼーション法を学べる。
2. 専門性: 心理専門家による指導で、科学的根拠に基づいた信頼できるプログラム。
3. 環境改善: 職場のコミュニケーションが円滑になり、チームとしての結束力を高める効果が期待できる。
4. 効果持続: 長期的に役立つ知識とスキルで、従業員の働き方や生活全般にポジティブな影響を与える。
お客様の声
「自分が無意識に取っていた行動が部下に影響を与えていたことに気づけた。特にアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)について学び、公平でフラットな視点を持つ努力が大事だと気づいた」
講師からのメッセージ

MIE ASAHARA淺原 美惠
心身の健康が個人や組織の成功を支える重要な要素となる現代において、メンタルヘルスへの理解と実践は欠かせません。私の研修は、自己ケアの方法から他者への配慮、さらには職場全体の心理的安全性を高める具体的なスキルに至るまで、幅広く学べる内容となっています。特に管理職の皆様には、部下のストレスサインに気づき、適切に対応するための実践的なツールとなり、チーム全体のパフォーマンスが向上し、より健康的で生産的な職場環境を築く一助となるでしょう。心の健康を見つめ直し、自身やチームをより良い方向に導く機会として、この研修にぜひご参加ください。皆様の職場がより豊かで明るい場所となるよう、全力でお手伝いいたします。
この講師の詳細ページへこの研修について問い合わせる